先日読書についての学びの中で、読書中のシンクロニシティについて知った。同時並行で読んでいた本が相互補完的に説明し合うことが起きる。Aという本で抱いた疑問への答え(ヒント)をBという本からもうらうといったこと。Aという本を一旦放り出してBに移ると、そこにAの説明がわかりやすく書いてあったりする。そしてAに戻るといったこと。
その後で体験した。
池田晶子さんの本→プラトンの『パイドン』と読み進めていたが。止まった。ちょっとわからなくなって止まった。わからないところを繰り返し読むけれど、読書のフローが失われたので一旦止めた。
先日、高橋巖先生の新しいご著書(『神秘学入門』)が出版されたので購入した。本屋さんで見つけて嬉しくなってすぐに購入して本棚に置いておいた。すぐに読むのではなく、めくる程度にパラパラと眺めていた。
そのパラパラと開いた中(神秘学の原風景)に、『パイドン』のことが書かれている。ソクラテスとの問答の中で一体何が言われているのかが、高橋先生の言葉で書かれており、それが神秘学の原点とも書かれていた。自分のつまづきへの助け舟のように深く入ってきた。
この体験というのはとても面白い。
人が経験したことを聞いて、「へぇ、そんなことってあるのか」と思っている間は半信半疑でいる。
ところがそのことを一旦体験(経験)してしまうと、有無を言わせず起きてしまったことなので、ああ、やっぱりこういうことはあるのだという他なくなる。そうして体験してみると本当に興味深い。不思議とは言えないほど、頻繁にあることらしい。そんなこと別に不思議でもなんでもないと思われる人もいるだろう(自分の興味のある本はどこか共通しているから、似たような内容が自ずと提示されているだろうからと)。そうした考えも一理あるとも思う。
ただ、驚くのはその人が驚きたくって驚くわけではないので、各自の中で驚きが勝手に起こるのだから、驚く人が驚けばいいということかもしれない。
本は最後まで読まなくても良いとも学んだ。2-3ページ読むだけでも良いと。自分にとってそのときに必要なことばは自ずともたらされる、と。
先日も夢中で読んでいた本をいとも簡単に放り出した。しばし放置していた。数週間ぶりに、また何気なく開くと、そこに自分に必要なことばが書かれている。釘付けになる。ことばが自分に向かって飛び出しているように感じる。これが読書というものかもしれないと。しかし、必要なことばというのは決してやさしくない。救われようと思っていても、えぐられることもある。本当の読書はやさしくないものかもしれないと思った。
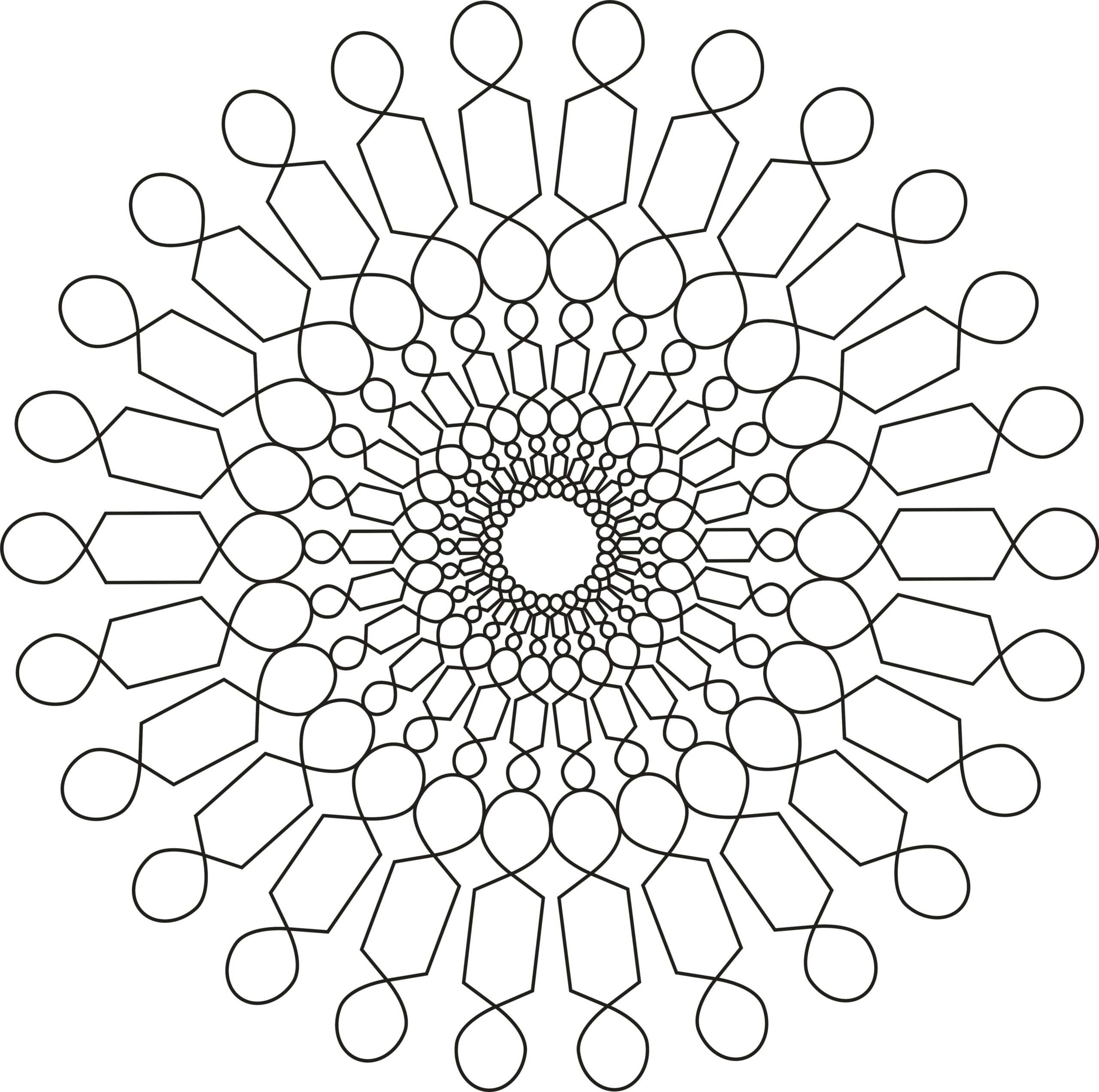


コメント